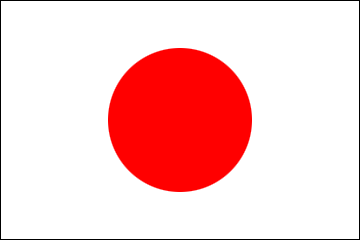ホーチミン国家政治学院(HCMA)・日本大使館共催 国際シンポジウム「越日関係50年の振り返り及び新たな発展ビジョン」 山田大使の開会挨拶及び発表
令和6年1月26日
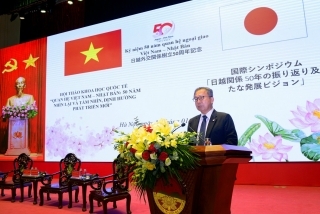

「日本の対外政策におけるベトナムの位置づけ」
1.ご挨拶
●グエン・ミン・ヴー(Mr. Nguyen Minh Vu)筆頭外務次官
●ファン・アイン・ソン(Mr. Phan Anh Son)各国友好組織連合会会長
日越外交関係樹立50周年であった2023年は、両国間のあらゆるレベルにおいて、過去最高の状況にあると評される今日の日越関係を反映して、数多くの素晴らしい交流や記念行事が開催されました。
中でも、昨年11月の岸田総理とトゥオン国家主席との首脳会談では、両国関係を「アジアと世界の平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に引き上げるという歴史的な決定がなされました。そして翌12月には、日ASEAN特別首脳会議に際して訪日されたチン首相と岸田総理との間で日越首脳会談が開催され、両国の「包括的戦略的パートナーシップ」の具体化について内容の濃い意見交換が行われたところです。
今後、我々は、過去50年間に培われてきた日越両国の関係を、「包括的戦略的パートナーシップ」という新たな名称に相応しい内実を備えたものへと更に大きく発展させていく必要があります。その記念すべき第一歩として、本日、日越関係を様々な分野で支えてくださる皆様をお迎えしてホーチミン国家政治学院と共にシンポジウムを開催する運びとなったことを誠にうれしく思います。
まず、シンポジウムの開催にご尽力されたホーチミン国家政治学院のグエン・スアン・タン院長をはじめ関係者の皆様、シンポジウムにご登壇いただくベトナム側の皆様及び日本側の皆様、さらにお集まりいただいたすべての学院生の皆様に、心より敬意を表します。
御存知の通り、ホーチミン国家政治学院は、党政治局員であるタン学院長の下、将来を嘱望された党や政府の幹部・行政官たちが切磋琢磨して研修を行う、ベトナムにおける最も権威のある学院です。そして、このホーチミン国家政治学院は、日本国大使館にとっても日頃から様々な協力を行っている最も重要なカウンターパートの一つでもあります。本日のシンポジウムには、日越関係の第一線で活躍されている実務者や研究者の方々、そしてベトナムの将来を担う多くの若い学院生の皆様がお集まりになられています。日越両国が、次の50年に向けて新たな一歩を踏み出す場として、本シンポジウム程相応しい機会はないのではないでしょうか。
現在の日越関係は、政治、経済をはじめあらゆる面で過去最高の状態にあると言われています。本日は、この場をお借りして、なぜここまで日越関係は急速に緊密化したのか、今後の日越関係はどうあるべきか、について私の考えを述べたいと思います。
日越関係の急速な緊密化は、両国の政治的・経済的な利益の一致によりもたらされていることは言うまでもありません。又、地域や世界の戦略環境が大きく変化する中で、日越協力の重要性は、両国は勿論、地域や世界にとっても益々高まりつつあります。これらの点については、後半部分でお話をすることとしたいと思います。
一方、今日のこれほどまでに急速な両国関係の緊密化を、そうした経済的・政治的な利益や地域・世界情勢の文脈のみで説明することは難しいのではないでしょうか?私は、両国関係の急速な緊密化の背景には、日越両国のみに働く独特の要因、つまり、日越両国の長い歴史的、文化的な繋がりによって無意識のうちに生み出されているユニークな「共感と共鳴」があるのではないかと考えています。
ベトナムは東南アジアの中では地理的にはもちろん、歴史的、文化的に見て、北東アジアに最も近い国です。日本とベトナムとの間では歴史的に様々な交流が記録されてきました。先ずここで、日越の歴史的交流のいくつかの例をご紹介したいと思います。
8世紀には、林邑僧(りんゆうそう)である仏哲が、奈良・東大寺の大仏開眼式のために来日し、「林邑楽」(迦陵頻伽(かりょうびんが)の舞)を奉納したという逸話があります。仏哲が伝えた林邑楽は、日本の雅楽にも影響を与えたと言われています。
16世紀から17世紀にかけては、朱印船交易が日越両国を深く結びつけました。徳川幕府が発行した朱印状の渡航先はベトナムが圧倒的に多く、家康はベトナム産の香木(伽羅、沈香)を好んだと言われています。当時ベトナム中部の港町ホイアンには大きな日本街が存在し、日本橋が架けられ、ベトナムから日本には陶器や織物などがもたらされました。広南グエン氏の貴婦人・アニオー姫と長崎の商人・荒木宗太郎の間のラブストーリーは今も語り継がれています。
このような両国の長い歴史的な交流に加え、儒教や大乗仏教の影響の強い精神文化や漢字を語源とするボキャブラリーが多いことなど、ベトナムと日本をはじめとする北東アジアの国々との間には、様々な文化的、精神的な共通性があります。私はこれをベトナムの「北東アジア性」と呼んでいます。そして、この長い歴史の中で培われてきたベトナムの「北東アジア性」が、日本人とベトナム人との間に無意識のうちに「共鳴と共感」を生み出しているのではないかと私は考えます。ベトナムの勤勉な若者が汗をかく姿に感銘を受けたり、ベトナムを旅行して田園風景や地元の人々とのふれあいに郷愁の念を感じたり、ベトナムの人々に心地よく受け入れられる日本のアニメや映画、音楽があったりと、その例は枚挙にいとまがありません。
そして、こうした精神的な部分での共通性によって支えられた両国の人と人とのつながりや好意的な国民感情は、日越関係を考える上で間違いなく最も重要な財産となっています。今日の日越関係が最良と言われるまでに急速に緊密化した背景には、こうした「共感・共鳴」に基づく日越の人と人とのつながりがあることを、まず指摘したいと思います。
そして、このような日越の人と人とのつながりを大切にし、より強固なものにしていくことこそが、今後の日越関係をよりよいものとしていく確かな礎となります。そのためには、国と国との関係はもとより、草の根レベルや地方レベル、次世代間といった様々な層で、文化・スポーツ、観光等を通じた人的交流を幅広く展開していくことが極めて重要です。その点、昨年、日越外交関係樹立50周年を慶賀して、日越双方の各地で500を超える記念事業が開催されたことは非常に有意義でした。在越日本国大使館としては、今年以降も皆様の協力を得つつ、このモメンタムを活かしていきたいと思っています。
これまでの部分で私は、日本とベトナムの間には最良の二国関係を築くための歴史的、文化的な素地が既に備わっていること、即ち両国の人々の間には長い時間を通じて培われた無意識の「共感と共鳴」が働いている、そのようなお話をしました。
次の後半部分では、今日の情勢に目を転じて、現在、地域や世界で進んでいる政治安保面や経済面での戦略環境の大きな変化が、日越関係を更なる高みへと引き上げようとしていることについてお話し申し上げたいと思います。
そして私は、昨年11月のヴォー・ヴァン・トゥオン国家主席の公式訪問の際に、日越両国の首脳が、両国関係を「アジアと世界における平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に引き上げる決定をしたのは、地域や世界の戦略環境の大きな変化を踏まえた英断であったと考えています。
日本の一貫した立場は、▽「力による支配」に反対し国際法の誠実な順守を通じた「法の支配」を目指すこと、▽力や威圧による一方的な現状変更の試みは決して認めないこと、▽国連憲章の原則の重大な違反に対抗するために協力すること、です。その上で、国際協調の潮流を強化していくためには、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序や開放性、包摂性、透明性、国際法の尊重といった諸原則に、国際社会を構成する全ての国と地域が立ち返る必要があります。
日本は、2016年に「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」という政策を発表し、以降現在に至るまでFOIPの実現に向けた取組を、考え方を共有する国々と連携しつつ戦略的に推進してきました。その結果、今やFOIPは、国際社会において幅広い支持を集めており、様々な協議や協力が進んでいます。ASEANが推進するAOIP(インド太平洋に関するASEANアウトルック)もFOIPと共通の原則を追求するものです。そして、日本としては、インド洋と太平洋を結ぶ地政学上の要衝に位置するベトナムは、FOIPを実現する上で要となるパートナーであると考えています。昨年11月、日越関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることを発表した共同声明の中でも、FOIP 実現に向けた様々な記述が盛り込まれました。
また、昨年11月の日越共同声明においては、日越両国が防衛装備品・技術の移転を含めた各種の防衛協力を進めていくこと、日本が新たに導入した「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の枠組みでの協力を検討していくこと、等が確認されました。また、昨今の国際情勢を踏まえ、海洋安全保障、海上保安に関する協力や治安、インテリジェンス、警察分野等の多岐にわたる分野で協力を拡大することについても日越両国の首脳の認識は一致しています。
(ii)経済分野における日越協力
今日の地域や世界における戦略環境の大きな変化は、世界的なサプライチェーンのシフトやDXやGX等の技術革新を通じて日越の経済関係にも追い風をもたらしています。また、ベトナムの高い経済成長、若い人口構成、豊富かつ良質な労働力、拡大する市場、台頭する中産階級といった魅力的な要素も、日本を含め世界各国からFDIをベトナムに引き寄せる誘因となっています。
今日、日本企業がベトナムに対して高い投資意欲を有していることは、各種調査にも表れています。例えば、2023年のJETROの調査では、ベトナムは、日本の大企業の進出意欲が世界で最も高い国(31.7%)となっており、さらに6割近くの日本企業がベトナムでの事業拡大を検討しています。
このような状況を踏まえ、昨年12月、岸田総理とチン首相は、経済分野における協力の強化が「包括的戦略的パートナーシップ」を更に深化させるために不可欠な原動力であるとの認識で一致しました。これは、日本とベトナムとの間の経済分野での協力が、今日の地域・世界情勢の下において戦略的意義を有することが確認されたという意味でも極めて重要です。
(ベトナムの近代化・工業化)
また、昨年11月の日越共同声明の中で、日本は、ベトナムの近代化・工業化を支援するとのコミットメントを再確認しました。本日もERIAから関連の発表がありますが、今後、ベトナムが工業化・近代化を達成し、高所得国・先進国入りを実現するためには、大規模な社会経済インフラの整備や国内産業の育成、そして、これらを可能にする経済・産業構造の転換、高度先進技術の取得に係る海外投資の呼び込みといった様々な課題があります。日本は、こうした分野でのベトナムとの協力を継続、強化します。
(ODA協力)
ODAについて申し上げれば、昨年12月、チン首相と岸田総理は2023年度の日本のODA供与額が2017年度以来初めて1000億円を超えたことを歓迎し、両国が、日本のODAを再活性化し、ベトナムにおける大規模で質の高いインフラ開発プロジェクトを促進するため、相互協力を一層強化していくことを確認しました。又、過去数年、日越のODA協力は、プロジェクト実施の遅延等の様々な課題に直面していますが、それらの諸課題を、両国首脳の強いリーダーシップの下で、日越双方の政府が関与し、迅速に解決していくことが確認されたことも首脳会談の大きな成果でした。
(DX/GX)
また、急速な技術革新がグローバルな戦略環境に大きな影響を及ぼす中で、今後は日越が、デジタル・トランスフォーメーション(DX)やグリーン・トランスフォーメーション(GX)等の新たな分野で、協力を進展させることが両国首脳間で確認されたことも、日越関係の新たな進展だと考えています。
DXの分野では、日本とベトナムの双方において、新たな投資や開発、人材育成等に向けた動きが生まれています。日本としては、DX分野において、ベトナムと共創のパートナーとして連携を強化したいと考えています。DX分野の協力は、日越協力の新たなフロンティアであり、大きなポテンシャルを持ったものであると考えます。
また、ベトナムは2045年の高所得国入りを目指すと同時に、2050年のカーボンニュートラル実現という野心的な目標を掲げています。経済成長とカーボンニュートラルという二つの目標をいかに実現させていくか?これはベトナムにとって非常にチャレンジングなテーマであり、又、地球規模の気候変動問題への対処という観点からも、避けては通れない課題です。これについては、昨年、日本は岸田首相のイニシアティブにより、アジア各国の実情に合わせたカーボンニュートラルの実現を目指す「アジア・ゼロエミッション共同体 (AZEC) 構想」を立ち上げました。この枠組みの下で、日本は、ベトナムの実情に合わせたGX分野の協力を加速化していきます。
(ベトナム人材)
そして、最後にお伝えしたいのが「人材」についてです。ベトナムの目覚ましい経済成長には、高い技能や意欲を有するベトナム人材の存在が大きいものと考えています。また、現在、日本で働く外国人労働者の約4分の1はベトナム人材であり、彼らが両国の経済発展に果たしている役割は計り知れないものがあります。
ベトナムが近代的な工業化を目指し、ITなどの分野における高度人材の育成に注力していることからも、今や、ベトナム人材に対し、日本のみならず、世界中の企業が注目しています。こうした状況において、日本は、今や我々は有能なベトナム人材を「選ぶ側」ではなく、むしろベトナム人材の方から「選ばれる側」に立っているという事実を謙虚に受け止めるべきだと私は考えます。日本がベトナムにおける人材育成に貢献していく一方で、日本自身も彼らが持つ専門性をビジネスに上手く取り込み、彼らが活躍できる機会を増やしていく、そんな環境や循環を両国で整えていくことが、この分野における発展の鍵であると考えます。
ベトナム人材は、日本にとって、もはや安価な労働力ではなく、日本経済を活性化するために不可欠な原動力です。日越双方でベトナム人材が活躍できる道筋を整えていくことが、私達に今求められていると考えます。
3.まとめ
さて皆さん、これまでお話し申し上げてきたように、日越両国の関係は、長い歴史的、文化的、精神的な繋がりが生み出した独自の「共感と共鳴」を基盤とし、今日の地域や世界の戦略環境の大きな変化が追い風となって、未来に向けてさらなる大きな発展が展望されます。私は、日越関係を「地域と世界の平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることが決定された日越外交関係樹立50周年、即ち2023年は、後世に振り返った折に、日越関係を、対等の土俵に立って、未来に、そして世界に向け、大きく飛躍させる歴史的な節目となった年、と評価されるようになるのではないかと考えます。
次の50年に向け、日越関係を更に大きく飛躍させるためには、日越双方が様々な分野でお互いの叡智を結集させることが必要です。本日ご登壇されるベトナム側及び日本側双方の第一級の政治家・研究者・実務家の皆様により、活発で有意義な議論が行われることを期待しております。
外交関係樹立50周年を契機に、日越関係が未来へ、そして世界へと一層大きく飛躍することを願い、私の発表とさせていただきます。御静聴ありがとうございました。
1.ご挨拶
- グエン・スアン・タン・ホーチミン(Mr. Nguyen Xuan Thang)党政治局員・中央理論評議会議長・ホーチミン国家政治学院長
●グエン・ミン・ヴー(Mr. Nguyen Minh Vu)筆頭外務次官
●ファン・アイン・ソン(Mr. Phan Anh Son)各国友好組織連合会会長
- グエン・フォン・ガー(Ms. Nguyen Phuong Nga)前外務次官・前各国友好組織連合会会長
- ホーチミン国家政治学院の関係者、学院生ほかベトナムの皆様、
- 日本からご列席の皆様
日越外交関係樹立50周年であった2023年は、両国間のあらゆるレベルにおいて、過去最高の状況にあると評される今日の日越関係を反映して、数多くの素晴らしい交流や記念行事が開催されました。
中でも、昨年11月の岸田総理とトゥオン国家主席との首脳会談では、両国関係を「アジアと世界の平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に引き上げるという歴史的な決定がなされました。そして翌12月には、日ASEAN特別首脳会議に際して訪日されたチン首相と岸田総理との間で日越首脳会談が開催され、両国の「包括的戦略的パートナーシップ」の具体化について内容の濃い意見交換が行われたところです。
今後、我々は、過去50年間に培われてきた日越両国の関係を、「包括的戦略的パートナーシップ」という新たな名称に相応しい内実を備えたものへと更に大きく発展させていく必要があります。その記念すべき第一歩として、本日、日越関係を様々な分野で支えてくださる皆様をお迎えしてホーチミン国家政治学院と共にシンポジウムを開催する運びとなったことを誠にうれしく思います。
まず、シンポジウムの開催にご尽力されたホーチミン国家政治学院のグエン・スアン・タン院長をはじめ関係者の皆様、シンポジウムにご登壇いただくベトナム側の皆様及び日本側の皆様、さらにお集まりいただいたすべての学院生の皆様に、心より敬意を表します。
御存知の通り、ホーチミン国家政治学院は、党政治局員であるタン学院長の下、将来を嘱望された党や政府の幹部・行政官たちが切磋琢磨して研修を行う、ベトナムにおける最も権威のある学院です。そして、このホーチミン国家政治学院は、日本国大使館にとっても日頃から様々な協力を行っている最も重要なカウンターパートの一つでもあります。本日のシンポジウムには、日越関係の第一線で活躍されている実務者や研究者の方々、そしてベトナムの将来を担う多くの若い学院生の皆様がお集まりになられています。日越両国が、次の50年に向けて新たな一歩を踏み出す場として、本シンポジウム程相応しい機会はないのではないでしょうか。
- 日越間の歴史的、文化的なつながりから包括的戦略的パートナーシップへ
現在の日越関係は、政治、経済をはじめあらゆる面で過去最高の状態にあると言われています。本日は、この場をお借りして、なぜここまで日越関係は急速に緊密化したのか、今後の日越関係はどうあるべきか、について私の考えを述べたいと思います。
- 日越関係の緊密化の背景(歴史的、文化的繋がりによる「共感と共鳴」)
日越関係の急速な緊密化は、両国の政治的・経済的な利益の一致によりもたらされていることは言うまでもありません。又、地域や世界の戦略環境が大きく変化する中で、日越協力の重要性は、両国は勿論、地域や世界にとっても益々高まりつつあります。これらの点については、後半部分でお話をすることとしたいと思います。
一方、今日のこれほどまでに急速な両国関係の緊密化を、そうした経済的・政治的な利益や地域・世界情勢の文脈のみで説明することは難しいのではないでしょうか?私は、両国関係の急速な緊密化の背景には、日越両国のみに働く独特の要因、つまり、日越両国の長い歴史的、文化的な繋がりによって無意識のうちに生み出されているユニークな「共感と共鳴」があるのではないかと考えています。
ベトナムは東南アジアの中では地理的にはもちろん、歴史的、文化的に見て、北東アジアに最も近い国です。日本とベトナムとの間では歴史的に様々な交流が記録されてきました。先ずここで、日越の歴史的交流のいくつかの例をご紹介したいと思います。
8世紀には、林邑僧(りんゆうそう)である仏哲が、奈良・東大寺の大仏開眼式のために来日し、「林邑楽」(迦陵頻伽(かりょうびんが)の舞)を奉納したという逸話があります。仏哲が伝えた林邑楽は、日本の雅楽にも影響を与えたと言われています。
16世紀から17世紀にかけては、朱印船交易が日越両国を深く結びつけました。徳川幕府が発行した朱印状の渡航先はベトナムが圧倒的に多く、家康はベトナム産の香木(伽羅、沈香)を好んだと言われています。当時ベトナム中部の港町ホイアンには大きな日本街が存在し、日本橋が架けられ、ベトナムから日本には陶器や織物などがもたらされました。広南グエン氏の貴婦人・アニオー姫と長崎の商人・荒木宗太郎の間のラブストーリーは今も語り継がれています。
このような両国の長い歴史的な交流に加え、儒教や大乗仏教の影響の強い精神文化や漢字を語源とするボキャブラリーが多いことなど、ベトナムと日本をはじめとする北東アジアの国々との間には、様々な文化的、精神的な共通性があります。私はこれをベトナムの「北東アジア性」と呼んでいます。そして、この長い歴史の中で培われてきたベトナムの「北東アジア性」が、日本人とベトナム人との間に無意識のうちに「共鳴と共感」を生み出しているのではないかと私は考えます。ベトナムの勤勉な若者が汗をかく姿に感銘を受けたり、ベトナムを旅行して田園風景や地元の人々とのふれあいに郷愁の念を感じたり、ベトナムの人々に心地よく受け入れられる日本のアニメや映画、音楽があったりと、その例は枚挙にいとまがありません。
そして、こうした精神的な部分での共通性によって支えられた両国の人と人とのつながりや好意的な国民感情は、日越関係を考える上で間違いなく最も重要な財産となっています。今日の日越関係が最良と言われるまでに急速に緊密化した背景には、こうした「共感・共鳴」に基づく日越の人と人とのつながりがあることを、まず指摘したいと思います。
そして、このような日越の人と人とのつながりを大切にし、より強固なものにしていくことこそが、今後の日越関係をよりよいものとしていく確かな礎となります。そのためには、国と国との関係はもとより、草の根レベルや地方レベル、次世代間といった様々な層で、文化・スポーツ、観光等を通じた人的交流を幅広く展開していくことが極めて重要です。その点、昨年、日越外交関係樹立50周年を慶賀して、日越双方の各地で500を超える記念事業が開催されたことは非常に有意義でした。在越日本国大使館としては、今年以降も皆様の協力を得つつ、このモメンタムを活かしていきたいと思っています。
- 今日の地域・世界情勢の大変化と日越関係
これまでの部分で私は、日本とベトナムの間には最良の二国関係を築くための歴史的、文化的な素地が既に備わっていること、即ち両国の人々の間には長い時間を通じて培われた無意識の「共感と共鳴」が働いている、そのようなお話をしました。
次の後半部分では、今日の情勢に目を転じて、現在、地域や世界で進んでいる政治安保面や経済面での戦略環境の大きな変化が、日越関係を更なる高みへと引き上げようとしていることについてお話し申し上げたいと思います。
そして私は、昨年11月のヴォー・ヴァン・トゥオン国家主席の公式訪問の際に、日越両国の首脳が、両国関係を「アジアと世界における平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に引き上げる決定をしたのは、地域や世界の戦略環境の大きな変化を踏まえた英断であったと考えています。
- 政治安保面における日越協力
日本の一貫した立場は、▽「力による支配」に反対し国際法の誠実な順守を通じた「法の支配」を目指すこと、▽力や威圧による一方的な現状変更の試みは決して認めないこと、▽国連憲章の原則の重大な違反に対抗するために協力すること、です。その上で、国際協調の潮流を強化していくためには、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序や開放性、包摂性、透明性、国際法の尊重といった諸原則に、国際社会を構成する全ての国と地域が立ち返る必要があります。
日本は、2016年に「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」という政策を発表し、以降現在に至るまでFOIPの実現に向けた取組を、考え方を共有する国々と連携しつつ戦略的に推進してきました。その結果、今やFOIPは、国際社会において幅広い支持を集めており、様々な協議や協力が進んでいます。ASEANが推進するAOIP(インド太平洋に関するASEANアウトルック)もFOIPと共通の原則を追求するものです。そして、日本としては、インド洋と太平洋を結ぶ地政学上の要衝に位置するベトナムは、FOIPを実現する上で要となるパートナーであると考えています。昨年11月、日越関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることを発表した共同声明の中でも、FOIP 実現に向けた様々な記述が盛り込まれました。
また、昨年11月の日越共同声明においては、日越両国が防衛装備品・技術の移転を含めた各種の防衛協力を進めていくこと、日本が新たに導入した「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の枠組みでの協力を検討していくこと、等が確認されました。また、昨今の国際情勢を踏まえ、海洋安全保障、海上保安に関する協力や治安、インテリジェンス、警察分野等の多岐にわたる分野で協力を拡大することについても日越両国の首脳の認識は一致しています。
(ii)経済分野における日越協力
今日の地域や世界における戦略環境の大きな変化は、世界的なサプライチェーンのシフトやDXやGX等の技術革新を通じて日越の経済関係にも追い風をもたらしています。また、ベトナムの高い経済成長、若い人口構成、豊富かつ良質な労働力、拡大する市場、台頭する中産階級といった魅力的な要素も、日本を含め世界各国からFDIをベトナムに引き寄せる誘因となっています。
今日、日本企業がベトナムに対して高い投資意欲を有していることは、各種調査にも表れています。例えば、2023年のJETROの調査では、ベトナムは、日本の大企業の進出意欲が世界で最も高い国(31.7%)となっており、さらに6割近くの日本企業がベトナムでの事業拡大を検討しています。
このような状況を踏まえ、昨年12月、岸田総理とチン首相は、経済分野における協力の強化が「包括的戦略的パートナーシップ」を更に深化させるために不可欠な原動力であるとの認識で一致しました。これは、日本とベトナムとの間の経済分野での協力が、今日の地域・世界情勢の下において戦略的意義を有することが確認されたという意味でも極めて重要です。
(ベトナムの近代化・工業化)
また、昨年11月の日越共同声明の中で、日本は、ベトナムの近代化・工業化を支援するとのコミットメントを再確認しました。本日もERIAから関連の発表がありますが、今後、ベトナムが工業化・近代化を達成し、高所得国・先進国入りを実現するためには、大規模な社会経済インフラの整備や国内産業の育成、そして、これらを可能にする経済・産業構造の転換、高度先進技術の取得に係る海外投資の呼び込みといった様々な課題があります。日本は、こうした分野でのベトナムとの協力を継続、強化します。
(ODA協力)
ODAについて申し上げれば、昨年12月、チン首相と岸田総理は2023年度の日本のODA供与額が2017年度以来初めて1000億円を超えたことを歓迎し、両国が、日本のODAを再活性化し、ベトナムにおける大規模で質の高いインフラ開発プロジェクトを促進するため、相互協力を一層強化していくことを確認しました。又、過去数年、日越のODA協力は、プロジェクト実施の遅延等の様々な課題に直面していますが、それらの諸課題を、両国首脳の強いリーダーシップの下で、日越双方の政府が関与し、迅速に解決していくことが確認されたことも首脳会談の大きな成果でした。
(DX/GX)
また、急速な技術革新がグローバルな戦略環境に大きな影響を及ぼす中で、今後は日越が、デジタル・トランスフォーメーション(DX)やグリーン・トランスフォーメーション(GX)等の新たな分野で、協力を進展させることが両国首脳間で確認されたことも、日越関係の新たな進展だと考えています。
DXの分野では、日本とベトナムの双方において、新たな投資や開発、人材育成等に向けた動きが生まれています。日本としては、DX分野において、ベトナムと共創のパートナーとして連携を強化したいと考えています。DX分野の協力は、日越協力の新たなフロンティアであり、大きなポテンシャルを持ったものであると考えます。
また、ベトナムは2045年の高所得国入りを目指すと同時に、2050年のカーボンニュートラル実現という野心的な目標を掲げています。経済成長とカーボンニュートラルという二つの目標をいかに実現させていくか?これはベトナムにとって非常にチャレンジングなテーマであり、又、地球規模の気候変動問題への対処という観点からも、避けては通れない課題です。これについては、昨年、日本は岸田首相のイニシアティブにより、アジア各国の実情に合わせたカーボンニュートラルの実現を目指す「アジア・ゼロエミッション共同体 (AZEC) 構想」を立ち上げました。この枠組みの下で、日本は、ベトナムの実情に合わせたGX分野の協力を加速化していきます。
(ベトナム人材)
そして、最後にお伝えしたいのが「人材」についてです。ベトナムの目覚ましい経済成長には、高い技能や意欲を有するベトナム人材の存在が大きいものと考えています。また、現在、日本で働く外国人労働者の約4分の1はベトナム人材であり、彼らが両国の経済発展に果たしている役割は計り知れないものがあります。
ベトナムが近代的な工業化を目指し、ITなどの分野における高度人材の育成に注力していることからも、今や、ベトナム人材に対し、日本のみならず、世界中の企業が注目しています。こうした状況において、日本は、今や我々は有能なベトナム人材を「選ぶ側」ではなく、むしろベトナム人材の方から「選ばれる側」に立っているという事実を謙虚に受け止めるべきだと私は考えます。日本がベトナムにおける人材育成に貢献していく一方で、日本自身も彼らが持つ専門性をビジネスに上手く取り込み、彼らが活躍できる機会を増やしていく、そんな環境や循環を両国で整えていくことが、この分野における発展の鍵であると考えます。
ベトナム人材は、日本にとって、もはや安価な労働力ではなく、日本経済を活性化するために不可欠な原動力です。日越双方でベトナム人材が活躍できる道筋を整えていくことが、私達に今求められていると考えます。
3.まとめ
さて皆さん、これまでお話し申し上げてきたように、日越両国の関係は、長い歴史的、文化的、精神的な繋がりが生み出した独自の「共感と共鳴」を基盤とし、今日の地域や世界の戦略環境の大きな変化が追い風となって、未来に向けてさらなる大きな発展が展望されます。私は、日越関係を「地域と世界の平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることが決定された日越外交関係樹立50周年、即ち2023年は、後世に振り返った折に、日越関係を、対等の土俵に立って、未来に、そして世界に向け、大きく飛躍させる歴史的な節目となった年、と評価されるようになるのではないかと考えます。
次の50年に向け、日越関係を更に大きく飛躍させるためには、日越双方が様々な分野でお互いの叡智を結集させることが必要です。本日ご登壇されるベトナム側及び日本側双方の第一級の政治家・研究者・実務家の皆様により、活発で有意義な議論が行われることを期待しております。
外交関係樹立50周年を契機に、日越関係が未来へ、そして世界へと一層大きく飛躍することを願い、私の発表とさせていただきます。御静聴ありがとうございました。